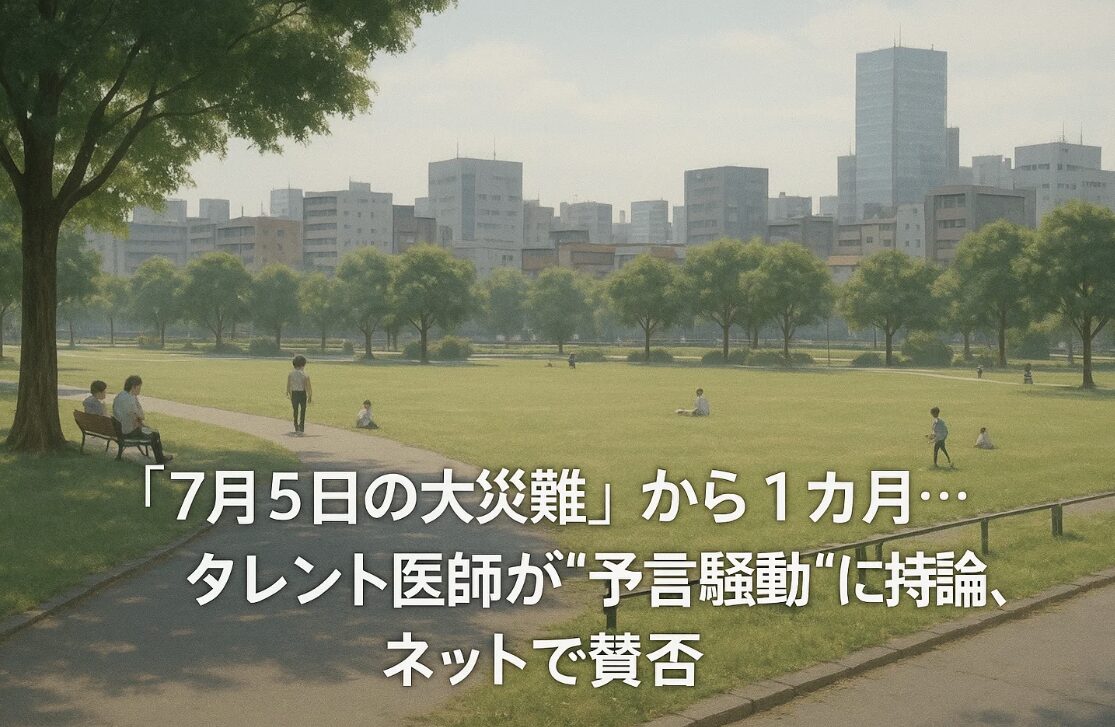2025年6月から7月にかけて話題となった「2025年7月5日に日本を襲う大災難」の噂は、多くの憶測を呼び、ネット上を騒がせました。
その発端となったのは、漫画家・たつき諒さんが過去の作品で描いた“予知夢”の内容です。やがてXデーと呼ばれるようになり、日本国内外で注目されましたが、実際には何も起こらず、現在は1カ月以上が経過しています。
そんな中、医師でタレントの木下博勝さんが「責任を取るべきだ」と発言し、SNS上で議論を呼んでいます。
- 「7月5日の大災難」噂の発端と拡散経緯
- 噂による社会的影響と防災意識の変化
- 情報発信と受信の責任を巡る議論の概要
「7月5日の大災難」は結局起こらず…現在の状況
「7月5日に大災難が起こる」という噂は、多くの人の不安を煽りました。
しかし当日は何事もなく、平穏な一日で終わりました。
現在はこの噂を振り返り、その経緯や背景について冷静に検証する動きが見られます。
噂が広がった経緯と背景
この噂のきっかけは、漫画家・たつき諒さんの著作に描かれた災害シーンとされます。
特定の日付が含まれていたため、一部の人々が「予言」として拡散しました。
特にSNSでは短期間で数万人規模に共有され、テレビやネットニュースでも取り上げられました。
背景には、近年の自然災害の頻発や、防災意識の高まりがあります。
また、コロナ禍以降の社会不安が、根拠の薄い噂でも信じやすくなる土壌を作っていたとも言えます。
こうした心理的要因が重なり、一見荒唐無稽な話でも拡散力を持ってしまったのです。
1カ月以上経った今の世間の反応
噂から1カ月以上が経過し、多くの人は「やっぱり何も起こらなかった」と安堵しています。
一方で、「防災意識が高まったことは悪くなかった」という肯定的な声もあります。
しかし、不安を煽る情報は慎重に扱うべきという意見がSNS上で広く共有され、情報リテラシーの重要性が再認識されました。
結果として、今回の件は「デマ拡散の教訓」として語られることになりそうです。
一部のメディアは特集を組み、噂の発生から収束までの経緯を検証しています。
今後は、同様の現象が起きても過剰に反応しないための知識や判断力が求められます。
発端となった漫画家・たつき諒さんの主張
今回の噂の中心人物とされたのが、漫画家のたつき諒さんです。
彼女の過去作に描かれた災害のシーンが、7月5日の大災難説と結びつけられました。
しかし、たつきさん本人は噂の広がりに戸惑い、冷静な見解を示しています。

作品に込めた意図と“予言”との違い
たつきさんはインタビューや書面で、作品はあくまでフィクションであり創作の一部だと明言しました。
物語の中で日付や災害描写を使ったのは、リアリティを高めるためであり、予言や霊感とは無関係としています。
つまり、意図せず現実の出来事と重なっただけであり、本人が未来予知を主張した事実はありません。
この点を誤解したまま情報が拡散され、SNSでは事実と創作の境界が曖昧になってしまいました。
創作と現実の混同は、情報社会で頻発する問題のひとつです。
今回のケースは、その危うさを象徴する事例といえます。

防災意識の高まりという副次的効果
一方で、噂が広まったことで、防災意識が向上するという副次的な効果もありました。
多くの人が非常用持ち出し袋を用意し、避難経路を確認するなどの行動を取ったのです。
自治体や防災関連団体も、この流れを利用して防災訓練や啓発活動を積極的に実施しました。
結果的に、根拠のない噂でも社会的効果を持ち得ることが証明された形です。
ただし、これは本来の望ましい形ではなく、正しい情報発信を通じた防災意識向上が理想であることは言うまでもありません。
噂をきっかけに得られた教訓を、今後にどう活かすかが問われています。
木下博勝さんが指摘した「責任論」
医師でありタレントとしても知られる木下博勝さんは、今回の噂に関して「誰が責任を負うべきか」というテーマに言及しました。
彼の発言はSNSで拡散され、賛否両論を呼びました。
当事者意識と情報発信の在り方について、多くの議論が巻き起こったのです。
Instagramでの発言内容
木下さんはInstagramで、「予言を広めて不安を煽った人には責任がある」とする考えを投稿しました。
さらに、噂を信じて行動した人々の心理にも触れ、情報を受け取る側のリテラシーの重要性を強調しました。
この発言は、根拠のない情報を拡散するリスクを可視化したといえます。
ただし、木下さんは名指しで誰かを批判したわけではなく、あくまで一般論としての警鐘でした。
そのため、一部では「冷静な指摘」と受け止められています。
しかし同時に、「特定の人物を連想させる」と感じた人から批判も上がりました。
批判と賛同、SNS上で割れる意見
木下さんの投稿に対して、賛同する声は「もっともな意見」「不安を煽るべきではない」というものでした。
一方、批判的な意見は「結果的に何も起こらなかったからといって責任を問うのはおかしい」とするものでした。
このように、情報発信の自由とその責任の境界は、非常にデリケートなテーマであることが浮き彫りになりました。
今回の議論は、ネット社会における倫理観の多様性を改めて示す結果となりました。
そして、このテーマは今後も災害情報や予測報道をめぐる場面で繰り返し問われる可能性があります。
重要なのは、発信者も受信者も互いに意識を高め、正確な情報のやり取りを心がけることです。
ネット上での議論と論点
「7月5日の大災難」をめぐっては、SNSや掲示板でさまざまな議論が交わされました。
議論は単なる噂話にとどまらず、情報を信じた人・信じなかった人双方の責任というテーマへ発展しました。
また、予言や噂とどう向き合うべきかという根本的な問題も浮かび上がりました。
「信じた側」の責任を問う声
一部のユーザーは、「信じて行動した人にも一定の責任がある」と主張しました。
その理由として、情報の真偽を自ら確認する姿勢の欠如や、拡散に加担したことを挙げています。
特に、感情的に反応して拡散することのリスクが問題視されました。
しかし、「被害者である信じた人を責めるべきではない」という反論も多く見られました。
この対立は、情報リテラシー教育の必要性を改めて浮き彫りにしました。
今後は個人の判断力だけでなく、社会全体での啓発が求められます。
予言や噂をどう受け止めるべきか?
ネット上では、「予言や噂は完全に無視すべき」という意見と、「念のため備えることは悪くない」という意見がありました。
前者は、不安を煽る情報の害を重視し、後者は防災意識の向上という副次的効果を評価しています。
つまり、噂との付き合い方は人それぞれであり、一概に正解はないという認識が広がっています。
ただし、共通しているのは、根拠を確認しないままの拡散は避けるべきという点です。
この原則は、災害情報に限らず日常的な情報共有にも通じます。
今回の騒動は、情報との距離感を見直す契機となりました。
7月5日の大災難を巡る一連の騒動まとめ

今回の「7月5日の大災難」騒動は、結果的に何も起こらず終わりました。
しかし、その過程で情報の拡散と受け止め方の課題が浮き彫りになりました。
また、防災意識やネットリテラシーの重要性を再確認するきっかけにもなりました。
一連の流れを振り返ると、まず漫画家・たつき諒さんの作品の一場面が噂の発端となりました。
その後、SNSで急速に拡散し、メディアでも取り上げられる事態に発展。
木下博勝さんをはじめ、著名人からも責任や情報発信のあり方について意見が出されました。
議論は「信じた側」「広めた側」双方の責任論や、予言や噂をどう受け止めるかというテーマに広がりました。
結果として、不安を煽る情報には慎重に向き合うべきという認識が強まりました。
同時に、誤情報やデマに惑わされないための知識や判断力が求められています。
個人的には、今回の出来事は災害時の備えを考えるきっかけになった点は良かったと思います。
結果的に何も起こらなかったとしても、日常的な防災意識の向上は社会にとって大きなプラスです。
大切なのは、正確な情報と冷静な判断を基盤に、日常的な備えを続ける姿勢ですよね?
今回のことを教訓にしていきたいと思います。最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
- 「7月5日の大災難」は噂のみで実際には起こらず
- 発端は漫画家・たつき諒さんの過去作の一場面
- SNSとメディアで急速拡散し社会現象化
- 噂拡散に対する責任論と情報リテラシーの議論
- 木下博勝さんが「不安を煽る責任」に言及
- 信じた側と広めた側双方の責任の是非が論点
- 副次的に防災意識が向上する効果も
- 不安を煽る情報は根拠確認と慎重な対応が必須
\ジャンル別ブログ紹介/
管理人が運営している、他の人気ブログはこちらから↓
- ▶ アニメ・ドラマ好きな方へ(生活に役立つ情報も!)
- ▶ 運気を整えたいあなたに(水回り×風水で家の運気アップ)
- ▶ 猫との暮らしを楽しみたい方へ(猫の気持ちと便利グッズを紹介)